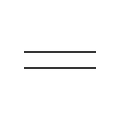全く異なる環境で暮らして見えたもの
こんにちは。私は、約半年間カンボジアのコンポンチュナン州でインターンシップに参加させていただいた、東京大学教育学部4年の後藤優奈と申します。この期間にたくさんの方々と出会い、たくさんのことを目にしました。ここでの生活を通じて、これまで「当たり前」だと思っていたことが、たくさんの人々の努力や支えによって成り立つものであることに、また日本の忙しない日常の中で生きていると忘れがちになってしまう大切なことに、気づくことができたように感じます。
自然
カンボジアには雨季と乾季があります。コンポンレーン郡農村開発事業チームの活動するコンポンレーン郡では、雨季になるとだんだんと水かさが上がり、乾季には歩いていける場所も、雨季には船でしか行けなくなってしまいます。
日本では、川の水かさが上がるのに備えて堤防があり、生活の場所に水が入ってこないように工夫します。ですが、カンボジアでは発想が逆です。毎年雨季には水位が数メートル上昇するため、それを見越して家が高く作られているのです。まずは自然があって、そのあとに人間の暮らしがある、という考え方です。他にも、農業研修やふりかけ製造では、その地域の資源を活用しています。他地域から持ってきたり、自然のものを人間の都合の良いように管理したりするのを前提とするのではなく、「そこにあるもので何ができるのか」を実践する姿を見て、自分の生活も、もっとエコにできる部分がたくさんあるのではないか、と思うようになりました。日本に帰って探してみたいと思います。

浸水域にあるコンポンレーン郡の学校も高床式
ひと
私は、ほとんどクメール語が話せません。ですが、カンボジアで出会った全ての人々が、私を温かく迎え入れてくれました。フィールドに行くとたくさんの人が挨拶をしてくれ、笑顔で話しかけてくれます。そして、クメール語の単語を教えてくれます。言葉は通じなくても、コミュニケーションは取れるし、笑い合うこともできます。
私は、クメール語が話せないからこそ、人と話す時は笑顔で、また相手の顔を見ながら話すように心がけました。そうしていると、たくさんの人が、様々なことを教えてくれました。ココナッツの葉で作るカゴの作り方やカンボジアの食べ物、家族のことなど。そのどれもが、コンポンレーン郡、コンポンチュナン州の人々の暮らしや、ひとの温かさに触れられるものでした。言葉が通じないことで戸惑う場面もありましたが、それでも相手を知ろうとし、尊重しようとする姿勢があれば、助け合い、協力することができます。この姿勢は、コミュニケーションの根幹であると実感しました。今後、言葉が通じる相手との会話でも、この姿勢を忘れないでいきたいと思います。

日常生活
まず、カンボジアの朝はとても早いです。学校は7時に、仕事は7時半に始まります。カンボジアでは「日の登った後に起きたら貧乏になる」と子供の頃に教わるらしいです。日本でも「早起きは三文の徳」と言うように、早起きはどこの国でも大事なことなのですね。
それから、カンボジアには昼寝の時間があります。昼休みは2時間あり、ご飯は基本的に家で食べます。ご飯の後ホストファミリーには「寝ておいで」と言われ、昼休みの後、オフィスでは「よく寝られた?」と聞かれます。最初は「昼寝はしないよ」と思っていましたが、やってみると午後の仕事も眠くなることなく集中できます。農業国だからこその文化かもしれませんが、昼寝の効果って、思った以上に大きいのだなと感じています。
ゴミ
コンポンレーン郡には、ゴミ回収の仕組みがありません。私にとってはこれが1番衝撃的だったかもしれません。日本では、ゴミを出したら回収してくれる人がいて、処理されます。ここに、どれだけの労力が割かれていて、どれだけ大事なものであるのかを、正直これまで考えたことはありませんでした。
ですが、ゴミ処理の制度を機能させるには、場所の選定から仕組み化、そして実際に、きちんと運用されるようになるまで、多くの人々が関わる必要があります。ゴミ回収の制度の確立は現地の人々に必要とされているものであり、多くの人が実現に向けて動いている現状を目の当たりにし、公衆衛生を保つために最重要な仕組みの1つだと実感しました。
コンポンレーン郡には、ゴミ回収のシステムがないため、ゴミの分別の習慣どころか、ゴミをゴミ箱に捨てる習慣もありません。道にはたくさんのゴミがよく落ちています。それでも、ゴミをきちんと集めて処理する重要性を伝えると、少しずつみんなの意識が変わっていきました。例えば、FIDRの実施する研修の会場には、ゴミは落ちていません。衛生環境が整っていないと健康に悪いということを、研修を通じて理解したからです。
「これは悪い」、「なんでできないんだ」と責めるのではなく「なぜこうしているのか」、「なぜこうするのがいいのか」を、互いが理解した上でより良い方法を選択し、改善していくことは、ゴミの分別だけでなく、あらゆる場面で持つべき視点だと感じました。

まだまだたくさん気がついたこと、感じたことはありますが、これまで暮らしてきた環境とは全く異なる場所で生活したことで、自分自身と向き合うことができ、また地球規模の課題や地域の課題を新たな視点で捉えることができたと考えています。このような機会を与えてくださったFIDRの皆さんに改めて感謝します。本当にありがとうございました。