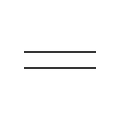驚きだらけのクラチェ生活
8月末から1カ月間、カンボジア・クラチェ州オフィスでインターンをさせていただいた、東京外国語大学カンボジア語科2年生の米倉彩恵です。カンボジアでの生活は日本との違いに驚くことが多かったのですが、現地の方々に助けていただきながら、気付きの多い毎日を過ごすことができました。
今回は、実際に滞在して気付いたカンボジアの特徴、首都プノンペンとクラチェの違いなどについて書こうと思います。
到着直後の2日間は首都であるプノンペンに滞在していました。インターンプログラム開始前日は、カンボジアに住む知人と食事をともにし、プログラム初日はプノンペンオフィスにて研修を受けました。前日に知人と観光がてら訪れたプノンペンのリバーサイドでは、22時以降も、小さな子どもたちが外で楽しく遊んだり、大人が集まってカンボジアの伝統的な遊びを行ったりと、日本ではなかなか見られない光景を目にし、驚く場面が多かったです。短い滞在でしたが、活気ある雰囲気を体感し、明るくエネルギッシュなカンボジアの一面に触れることができました。
プログラム2日目にはクラチェ州へ移動しました。プノンペンから車で約6時間かけて移動します。到着してまず感じたのは、首都との大きな違いです。高層ビルや配車サービス(タクシー配車アプリ)はなく、その代わりに雄大なメコン川(東南アジアで最長の川。カンボジアを東西に分けるように流れる。)が広がっていました。都市から地方へと舞台が移り、これから始まる生活に胸が高鳴る瞬間でした。
クラチェでの暮らしでは、プノンペンで見なかったものばかりで、さらに多くの発見がありました。通勤路の一本道では、人よりも牛や犬、鳥に出会う数の方が多いほど、動物たちが身近にいます。また、町の家屋はほとんどがカンボジアの伝統的な建築方法である高床式(蒸し暑い気候でも快適に過ごすことができ、雨季に洪水となっても浸水することが無いように、1階部分が柱のみとなり床が地面から離れている。)で、教科書で見た光景が目の前に広がっていることにも驚きました。正直、「もうカンボジアでは高床式の家は少ないのでは」と思っていた自分の先入観を反省しました。
食文化にも違いがあり、「レストランらしいレストラン」の数は数えられる程度しかありません。多くの飲食店は屋台のような簡易的なキッチンとパラソル付きのイートインスペースで成り立っていて、日常の食事すら新鮮な体験です。また、一日に何度も食事をする点は、「一日三食」が根付いている日本と大きく異なります。朝食の後に軽食を食べ、そのあと昼食を食べるのです。さらに、昼食の後にまた軽食を食べます。
人と人とのつながりも印象的です。ホストファミリーのお母さんと一緒に家の近くを散歩したとき、お母さんはふらっとご近所さんの庭に入って、立ち話をしていました。それが、一度ではなく、何度も。歩く時間よりも笑いあう時間の方が長く、気軽な交流が日常の自然な一部になっていることを感じました。また、街の人達が、知り合いを見つければ躊躇なくバイクのクラクションで合図している様子を見て、人々の距離の近さやコミュニケーションの取り方の自由さを改めて実感しました。
正直なところ、衛生観念や動物に対する考え方などの違いから、ショックを受けることもあります。例えば、鍋に入った大きなカエルを「サエ!みて、かわいいよ!」と見せられた時は倒れそうになりました。
しかし、この一週間での体験を通して、私は「違い」にただ驚くのではなく、それを理解し、自分の行動や考えに活かすことが学びにつながるのだと実感しました。「思っていたものと違った」という言葉は単なる感想ではなく、自分の価値観や先入観を見直すきっかけになりました。自分と異なる文化を持つ地域で働くということは、場所だけでなく、生活スタイルから働く人々まで、何もかもが違うということです。だからこそ、その地域の生活環境を理解することがとても大事だということにも気付きました。
このように、クラチェでの生活は日本ともプノンペンとも異なり、毎日が学びと気づきの連続です。現地の方々の温かさに支えられながら、この環境だからこそできる経験を大切にし、受け入れていただいていることに感謝しながら、インターンとして少しでも貢献できるよう努めて活動をおこないました。

自転車で通勤しています。

町のいたるところで牛と遭遇します。

ホストファミリーと食べるご飯の様子