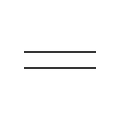プロジェクトの今~SOCDP 教員研修~
11月、オカルドゥンガ郡の小学校10校の教員約30名を対象に、「音楽科目」と「子ども中心の教育アプローチ」に関する7日間の研修を2グループに分けて開催しました。
同研修は昨年度にも別の18校の教員らを対象に開催され、その成果を耳にした地域行政及び校長らから要請をうけて、今回の研修が企画されました。FIDRはそれぞれの領域を専門とする講師2名を連れて、再び首都カトマンズからプロジェクト地へ赴きました。
昨年度の研修の様子はこちら
山岳地域のため移動が困難なことから、宿泊研修として全員泊まり込みで行われた本研修は、毎日朝8時半の瞑想からスタートしました。

研修は参加者が輪になって座り瞑想することから始まります
音楽科目
ネパールはダンスが大好きな国民性があるものの、「音楽科目」の授業を人生で一度も受けたことのない教員たちは、“リズムにあわせて、全員で一緒に歌う・手をたたく・踊る”、という初めての体験に最初は苦戦していました。合唱では自分の声だけでなく周りの声を聴きながら歌うことが必要ですが、 周りの声を聞かずに一人テンポが合わないまま歌ったり、手をたたくタイミングが周りとずれていても気付かなかったり…また、ハーモニウムの音にあわせて“ドレミファソラシド”の音階を歌うことも初めてです。なかなか音程がとれない教員もいましたが、この機会にしっかり学ばねば、という真剣な教員たちの表情が印象的でした。

ダンスを練習している教員たち
子ども中心の教育アプローチ
ネパールでは教科書の音読や、板書したものを生徒に復唱させる講義形式が一般的です。そこで、「子ども中心の教育アプローチ」では、講師が“身近にあるもの”を活用して、子どもたちの主体的な学びをサポートするアプローチを実演していきました。
例えば、算数の“位”の学習について。「一の位」「十の位」「百の位」について、日本の小学校ではおはじきを使いますが、ネパールの山岳地域に位置する学校にはそのような補助教材はありません。そこで、本研修ではマス目をひいた模造紙の上に小さな棒を置きながら、どのように子どもたちに教えたらよいかを講師が実演しました。
その他にも、子どもたちが算数を楽しみながら学べるような手法も実演しました。床に三重の円を描いた紙を置き、外側から「一の位」「十の位」「百の位」として、決められた位置からコインを投げます。コインが止まった場所の位とコインの数で点数を算出してグループごとの総合点を競うのですが、実際に体験した教員たちは大盛り上がりで、グループ同士の応援合戦がはじまったほどでした。

コインを投げるゲームの様子
このような実演に加え、教員として子どもたちとどう向き合うかについても、講師たちから助言がなされました。例えば、算数の問題に間違った回答をした教員がいた際には、「たとえ教室で子どもたちが間違った回答をしても、体罰をしてはいけないよ。体罰は子どもたちの学習意欲を後押しするものにはなりえないのだから」と真摯に伝えていました。
12月にはもう一つのプロジェクト地であるソルクンブ郡の小学校8校の教員約20名を対象に、同様の研修を開催します。その研修が無事完了すると、プロジェクト地に位置する計36校の教員約100名が同研修の受講を完了したことになります。
今回の研修に参加した教員たちが、学んだことをそれぞれの教室で活用し、より充実した授業を行うことができるよう、後押ししてまいります。そして、そうした授業を受けることで子どもたちの学びが深められ、子どもたちの可能性がより広がっていくよう、期待しています。